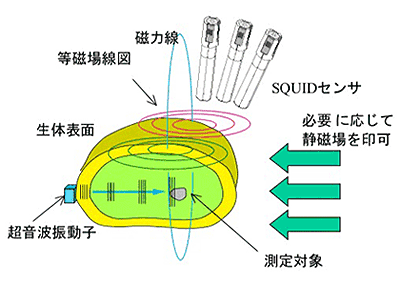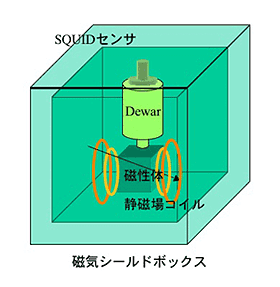| 研究代表 | 金沢工業大学先端電子技術応用研究所 教授 上原 弦 |
| U R L | http://wwwr.kanazawa-it.ac.jp/kit_ael/ |
| 参画機関 | 金沢工業大学、横河電機株式会社 |
1) SQUID:超電導量子干渉素子 脳磁計、心磁計は、ヒトや実験動物の生体信号を非侵襲で測定できるというメリットがあり、臨床現場や医学研究の現場で実用に供されている。この技術を更に高めるため、測定対象に機械的音響的あるいは磁気的な変調を与えることで従来の受動的なSQUID磁気計測では達成できなかった能動的なセンシングを行なうテーマである。すなわち磁気分布の活性化あるいは変調により、構造と機能の知見を同時に捉えられる装置を開発する。具体的には、測定対象に含まれる陽子を磁気的に活性化させることによる磁気イメージングする装置、磁性を空間的かつ時間的に変調することによる磁気イメージングする装置などを研究開発する。すなわち、磁気的な活性化による能動的センシングと機械音響的な活性化による能動的センシングである。これにより、医療応用においては大型機器の導入費用の削減を図り、被験者が低磁場曝露のメリットを享受できるようにし、ライフサイエンス関連分野においても動物実験の非侵襲な生体機能解析の効率化が期待できる。
磁気的な活性化による能動的センシングであるSQUID-MRIは従来のMRIと異なり、低磁場(地磁気レベル)での陽子の共鳴を検出するものであり周波数が10kHz以下になるがこれを低い周波数でも十分な感度をもつSQUIDで検出するものである。高磁場に被曝する危険を避けられるというメリットの他、共鳴周波数のQ値が高く分解能が向上するというメリットや、腫瘍の判別に有利であるなどのメリットが期待できる。機械音響的な活性化による能動的センシングであるSonomagnetometry 2)は、従来の形態の情報を得るだけの超音波エコー装置とは異なり、機械/音響的に励起される磁気をとらえることで磁場源の空間分布と時間変化を同時にとらえ、また機械/音響的反射の信号情報と統合することにより形態情報と機能情報をあわせて提示できる計測手法である。
2) Sonomagnetometry:超音波などで変調された磁場信号をSQUIDで検出するイメージング SQUID-MRIの実現はMEGとMRIが同一の装置で実現できることを意味しており、医療応用においては大型医療機器の導入費用の削減と都市における土地利用の効率化など大きな経済効果を与える。また、低磁場曝露の装置であるため非侵襲性が増すというメリットを被験者が享受できることになる。Sonomagnetometryの実現は、超音波エコー装置とMCG 3)/MEGの一体化によるメリットだけではなく、磁気的にターゲットされた治療薬が分布する様子を可視化する等により、Drug Delivery System研究などに有力なツールとなり、これを実験動物に適用することで最先端の基礎医学・創薬・バイオ・ライフサイエンス関連の研究分野の動物実験において非侵襲生体機能解析の効率化をもたらすものと考えられ、この分野での事業化が期待できる。
3)MCG:心磁図